しばらく間が空いてしまいましたが、前回は第22回芸術祭に「執行正俊バレエ団(N.Shigyo Ballet Troupe)」として参加したプログラムに寄せられた高田せい子さんの挨拶文と、祖父との長年の関係について紹介しました。
今回は、挨拶文の中でも紹介されていた、祖父の振付作品《ファウスト》について紹介したいと思います。『ファウスト』と言えば、ドイツの文人ゲーテが第1部を1808年、第2部を1833年に発表した彼の代表作です。
残念ながらこの作品を実際に観ることはできませんでしたが、ドイツが誇る文豪の代表作を、渡独経験のある祖父がどのように作品にしたのか、非常に興味があります。
また、本作は祖父、執行正俊が老ファウストを演じ、息子の執行伸宜が青年になったファウストを演じるという、親子共演作品です。


はじめにお断りしておくと、不定期配信にしてからは記事を書くのに時間をかけているので、文章も長くなりがち。読者のみんなも疲れたら途中で休憩して、好きな時に戻って来てね。
執行正俊振付作品《ファウスト》
まずはプログラムに記載されている、祖父による解説文を紹介します。
執行正俊振付作品「ファウスト」
研究室で生涯を送り、すでに老齢に達したファウストは、悪魔に魂を売り渡すことで青春を得る。街に出た彼は命令通り享楽と悪の道に耽るが、純粋なマルガレーテの恋により煩悶する。
しかし、悪の犠牲となったマルガレーテは、母や兄を失い、赤ん坊を池に投じた罪で死刑を宣告される……。それでもなお、彼女はファウストを想い、神を信じ続ける。罪の恐ろしさに苦しんだファウストは、ついに恋の炎と共に地獄の奈落へと落ちるが、マルガレーテの強い愛と神への祈りによって、二人は救われ、昇天する。
この作品は、「愛こそが人間が生きるうえでの究極の祈りである」 というテーマを描いている。
ファウストが青春を取り戻し、街へと繰り出す世界観を現代の社会に置き換え、刹那的な享楽と争いの中で利権を求めるメフィストを街の顔役として設定している。さらに、随所に仮面をかぶった火の女王やオベロンが登場するが、これは狂言回しの役割を果たし、常にファウストのそばで死の暗示を与える存在である。
現代にもファウスト的人物は存在する。
つまり、一生を研究のために捧げながら、人生を無駄に過ごした学者や芸術家、あるいは、教育ママに育てられ、出世コースをたどって勉強だけに明け暮れ、社会的に重要なポストに就いた者に見られることが多い。この作品では、ゲーテの『ファウスト』よりもツルゲーネフの『ファウスト』 からモチーフを取材してみた。
この挨拶文からは、祖父の作品が宗教的・精神的なテーマと、現代社会に対する批評性を併せ持っていたことが読み取れます。あらすじを読む限り、物語の構造はゲーテの「ファウスト」を元にしているようですが、ツルゲーネフ版の『ファウスト』からモチーフをとっているとあります。
ツルゲーネフの短編『ファウスト』(1856年)は、ゲーテの作品を登場人物が読むという構造を通して、知と愛、感情の目覚めを描いた内面的な物語です。
ツルゲーネフ版『ファウスト』のあらすじを簡単に紹介します。
語り手である「私」は友人パーヴェルのもとを訪れ、かつての恋人ヴェーラとの思い出にひたる。ヴェーラはゲーテの『ファウスト』に深い感動を覚え、その読書体験を通じて自身の内面を目覚めさせ、パーヴェルに恋心を抱く。しかしその激情に責任を感じたパーヴェルは彼女のもとを去り、物語は淡い痛みとともに終わる。
執行正俊版『ファウスト』とゲーテ版・ツルゲーネフ版との比較
ここからは祖父の《ファウスト》と、ゲーテ版・ツルゲーネフ版の共通点や相違点を比較してみます。
| 観点 | ゲーテ版・ツルゲーネフ版 | 執行正俊版『ファウスト』 |
|---|---|---|
| 主人公の設定 | ゲーテ:悪魔と契約する老博 ツルゲーネフ:知的読書を通じて感情が芽生える人物たち | ゲーテ版と同じ老博士だが、現代社会に生きる。 |
| メフィストの描写 | ゲーテ:悪魔そのもの ツルゲーネフ:不在 | 利権構造の象徴として“街の顔役”として登場。 |
| 舞台背景 | ゲーテ:中世ドイツ風の寓話的世界 ツルゲーネフ:ロシアの田舎 | 現代都市に置き換え、享楽と争いが交錯する競争社会。 |
| 救済の描き方 | ゲーテ:神の世界へと昇天 ツルゲーネフ:宗教的な救済は描かれない | マルガレーテの祈りと愛が魂の救済をもたらす。 |
| 表現形式 | ゲーテ:詩劇形式、壮大な構成ツルゲーネフ:内省的な心理小説 | モダンバレエを通じて、精神の葛藤と美を視覚化。仮面のキャラクターによる象徴表現も取り入れている。 |
執行正俊版『ファウスト』の特徴
祖父の作品は、ゲーテ版の壮大な構成を借りながら、登場人物の内面の葛藤に焦点を当てて、ツルゲーネフ的な心理の細やかさを取り入れている点に特徴があります。
以下に執行正俊版『ファウスト』の特徴をまとめてみます。
- 舞台を現代社会に移し、メフィストを利権を操る“街の顔役”として描写しています。
- 火の女王やオベロンといった仮面のキャラクターを配置し、死の象徴として機能させています。
- マルガレーテの愛と祈りによる救済を中心に据える構成を取っています。
- 煩悶するファウストの姿を、単なる悲劇ではなく再生と救いの可能性として描いています。
まず、時代設定を現代社会に移したことは大きな改編と言って良いと思います。これによって『ファウスト』が単なる昔話ではなく、現代に通じるテーゼを持った作品であるということが強調されます。
仮面の使用は、祖父のモダンダンスの師であるマリー・ウィグマンが、西洋ではそれまで単なるギミックとして使われていた仮面を、日本の伝統芸能である能から影響を受けて、象徴的な意味合いを込めて作品に登場させていました。ですから、祖父も同じように仮面を自身の創作に取り入れたと考えられます。
挨拶文にも「愛こそが人間が生きるうえでの究極の祈りである」と書いてあり、この点を中心主題に持ってきたことは大きな特徴です。ゲーテ版『ファウスト』でも、特に第2部のクライマックスでファウストがメフィストの契約を乗り越えて神の国へと昇天する場面がありますが、これはあくまでファウスト自身の行動によって導かれた結末です。
一方の執行正俊版はマルガレーテの愛と赦しがファウストを救済しているので、よく言えば利他的、悪く言えば他力本願なクライマックスになっています。
ここで気になるのは、いったいツルゲーネフ版『ファウスト』のどこをモチーフにしたのか?という点です。これは僕の仮説に過ぎませんが、バレエ作品は多くの場合、主役は女性です。ファウストを主人公として考えると他力本願に見えるこの作品も、マルガレーテを主人公として考えると、さまざまな困難の中で悩み、苦しみながらファウストを愛し、祈る姿は、ツルゲーネフ版におけるヴェーラの心理描写と響き合っており、祖父がこの短編から得たインスピレーションは彼女の内面表現に集約されていると考えられます。
なぜ祖父は『ファウスト』を振り付けたのか
1930年からドイツに留学し、マリー・ウィグマンのもとでモダンダンスを学んだ祖父は、帰国後、モダンダンスの流行には乗らず、バレエとモダンダンスを融合させたモダンバレエを追求してきました。
そんな祖父にとって『ファウスト』は、
- ドイツでの学びの象徴であり、
- モダンダンスとクラシックの融合を実践する格好の題材であり、
- 日本の舞踊界に対する問いかけでもあったのだと思います。
まとめ
執行正俊版《ファウスト》は、ゲーテの構造、ツルゲーネフの心理描写、ウィグマンの象徴性、そして能の霊性が融合した、東西の思想が交差した作品だったのではないかと想像します。
ゲーテの描いたファウスト像には、人間の努力や倫理的行動の中に“神のような普遍的な力”を見出す、汎神論的かつ人間中心の精神主義に基づいています。こうした思想はモダニズムと強く親和性を持っています。
一方で、ポストモダン以降の現代においては、こう言った人間中心のテーマは若干時代遅れの感もあります。
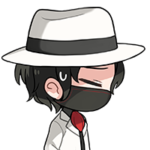
大震災、大津波に新型コロナウイルス、世界を覆う異常気象、シンギュラリティ*の到来。僕たちの世界は決して人間が中心に回っていないことは骨身にしみて分かっている。
*AI (人工知能)が人間の知能を超える、あるいはそれによって社会が大きく変化する転換点のこと
もし、祖父の息子である父、執行伸宜が、現代版の《ファウスト》を創るとしたら、この作品をどのように更新し、あるいは問い直すのでしょうか。
今や父も老ファウストを名乗れる年齢です。
じつは以前、父に執行正俊版《ファウスト》について聞いてみたことがあるのですが、とても若い頃にダンサーとして出演していたため、あまり覚えていないそうです。
それでも、僕は執行伸宜版《ファウスト》を、一度見てみたいと思っています。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
水曜・土曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

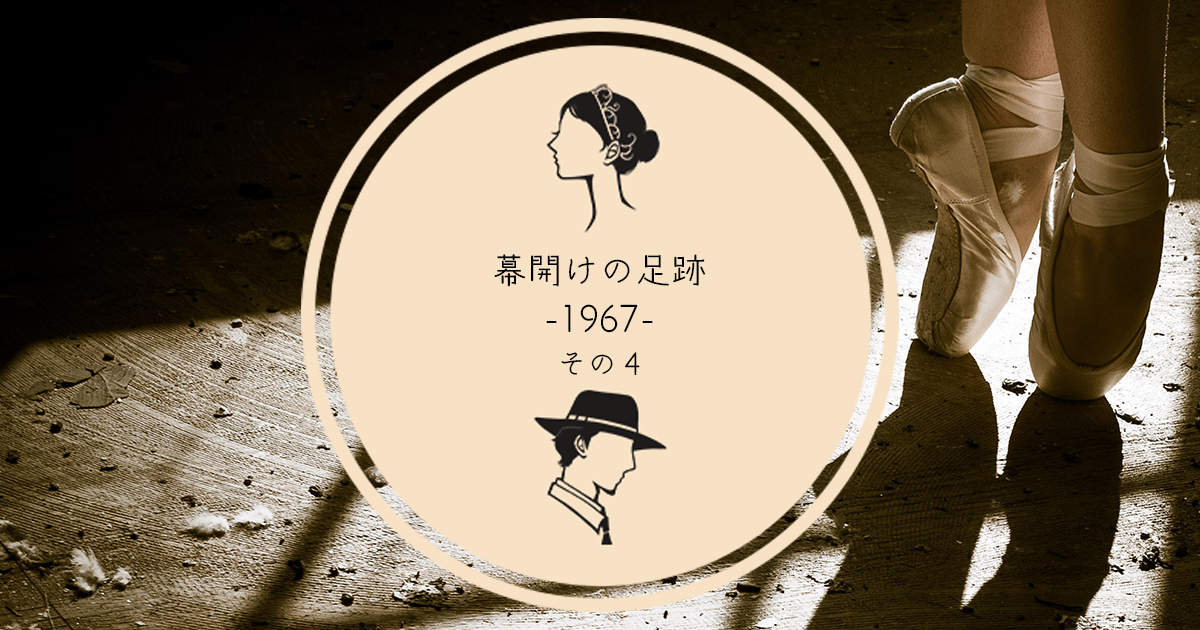

コメント